今回の事故でしきりに取り上げられている速度超過ですが、福知山線で設定された各地点の速度制限が、そもそも根拠のあるものなのかどうかということが、気になるところです。
というのも、ご存じない方が多いと思いますが、鉄道における最高速度については、転覆や脱線といった観点はなく、緻密に計算して設定されているものではありません。唯一、法令での基準があるとすれば、「踏み切りのある路線においては、非常ブレーキ後600m以内で停止しなければならない」と言う、国土交通省から出された技術基準だけです。つまり、600m以内で停止さえ出来れば、運転計画として作成することにより、いくらでも高速化することが可能です。
つまり、国土交通省はJR西日本の高速化について、明確な基準による指導が出来ない状況であったことがわかります。
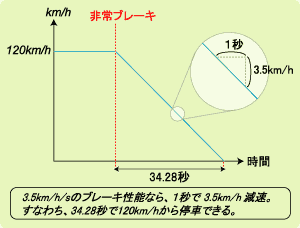 もちろん、現実問題として200km/hで走っている列車が600m以内で停止できるとは思えませんから、おのずと速度の上限は決まってきます。
もちろん、現実問題として200km/hで走っている列車が600m以内で停止できるとは思えませんから、おのずと速度の上限は決まってきます。
今回事故を起こした207系の場合、減速性能は 3.5km/h/s だそうです。これは、1秒間に3.5km/hの減速を行えることを示しており、右図を見ればわかるように120km/hから停止するまでにかかる秒数は単純計算で34.28秒。120km/hから0km/hまで直線的に減速するとすれば、半分の 60km/h(≒16.667m/s) を掛ければよいので、570m程度で停車できることがわかります。
これが、130km/hとなると停車まで670mかかることになり、法令違反です。なので、207系は最高速度が120km/hとなっているわけです。すなわち、現在の法令に基づく速度の上限は、路線によって決定されるものではなく、車体によって決定されるものと理解することも可能です。
つまり重要な点は、そもそもカーブにおいて根拠のある最高速度設定は行われていないということです。
記憶に新しいところでは、今回の事故現場において「脱線・転覆する速度は133km/hである」と言っていたにもかかわらず、最終的には「乗客が乗っているとわからない」と言うことになりました。そう、結局綿密なシミュレーションや実験を行っていないので、どれだけ出したら横転するかはわからないのです。極論を言えば、条件によっては70km/h以下でも脱線する可能性が0ではないかもしれません。
自動車の場合は、あまりに低すぎる制限速度ゆえ、裏通りなどでは有名無実になっているという意見もありますが、自身の危険性より歩行者や他の車への影響から制限を設けられています。すなわち、その速度を超過して、すぐにスリップしたり跳んで行ったりする危険はありません。また、死傷者など、事故の際の影響も、航空機や鉄道に比べると比較的軽微なことが多いと言えます。もちろん件数は桁違いですが。
新幹線の実験中に車輪の蛇行動で脱線しかけたと言う話がありました。しかし、これは乗客を乗せる前の実験段階であり、その後も繰り返し実験行い、ある程度の確証を得た上で制限速度を設定しました。現在でも、新造の新幹線が出るたびに延々と試験を行い、いまもJR西日本とJR東海の共同開発中の新型のN700系を試験していると聞きます。
それに対し、在来線の制限速度は、ダイヤ作成者のカンに頼るところが多く、シミュレーションしたものでも、実地試験をしたわけでもありません。すなわち、今まで大丈夫だったからという、悪い方でのカンが生きています。今回の現場の手前も、最高速度は120km/hに引き上げられ、運転士のカンに頼って70km/h制限のカーブを曲がることになりました。カンとカン、本当に安全が担保できそうな気がしません。
ところで、国土交通省から出されていた技術基準は、規制緩和の流れの中で「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に変更され、600mルールは無くなりました。
すなわち、速度の上限を決める法令は、私の知る限りありません(あれば教えてください)。
この中で最後の防護壁となるのは、国土交通省に必ず提出しなければならない、運行計画ですが、今回の福知山線については何のお咎めも無く受理されているわけです。
もちろん、JR西日本のように速度こそが最高のサービスだと、確信犯的に考えている事業者の運行計画に、難癖つけるのは難しいと思いますが、知らなかったで済まされる問題ではありません。JR西日本の垣内さんも、これほど深い自社の闇を全て理解していたわけでもなく、一連の騒ぎは降って沸いたような実感かもしれませんが、やはり知らなかったで済まされる問題ではありません。
今後、シミュレーションや実験などの客観的な裏付けを行い、根拠のある速度制限の方針を明確に打ち出し、安全が担保できる最高速度を設定していくことが、国に突きつけられた大きな課題ではないでしょうか?モラルを失った事業者と、全く咎めない所轄官庁、それも癒着つきとなれば、最悪の事態になったこともうなずけます。
列車の性能諸元
| 型式 | 製造開始年 | モーター | 出力 | 減速度 | 最高速度 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991年 | WMT100 | 155KW | 3.5km/h/s | 120km/h | 今回事故を起こした1両目〜4両目 | |
| 1994年 | WMT102 | 200KW | 3.5km/h/s | 120km/h | 今回事故を起こした5両目〜7両目。速度記録がされていた | |
| 2002年 | WMT102B | 220KW | 3.5km/h/s | 120km/h | ||
| 223系2000番代 | 1999年 | WMT102B | 220KW | 4.3km/h/s | 130km/h | 130km/hで走る新快速 |
- 今回事故を起こした列車は、前4両が旧型の0番代、後3両が中期型の1000番代でした。運転士は当日に繰り返しオーバーランをしていたようですが、モーター出力が前後でかなり異なる編成となり、電気ブレーキの操作が非常に困難だった可能性も考えられます。
- 最新の207系と223系は同様の出力のモーターを搭載しており、もはやブレーキ性能とギヤ比以外は、全く変わらないことがわかります。
関連情報
鉄道事業を始めるには:
→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ns/tetsuduki/tetsudou.htm
鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の制定について:
→ http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha01/08/081225_2_.html
207系型電車の諸元:
→ http://homepage3.nifty.com/canada/Urban/207-0~jp.html

コメント (7)
いわゆる "最高速度" は別として、カーブの場合、曲率に応じて制限速度が決まっているはずです。これは、脱線する可能性がある限界値より相当に低く設定されていますが、脱線に至らないまでも、遠心力の関係で乗り心地が非常に悪くなる等の事情によります。
ただし、カント扛上や振子車両の導入によって制限を引き上げることは可能です。といっても、前者には自ずから限度がありますし (カントをつけすぎると、カーブで停車した際にひっくり返る)、後者は車両側と地上側の両方で対応が必要です。
この件、マスコミ報道一般にもいえることですけど、「最高速度」の話と「カーブにおける制限速度」の話がごっちゃになっている傾向があるように思えます。
あと、車輌性能の話ですけど、モーター出力が違っていても、電動車と付随車の比率、ギア比の違いなどのファクターも絡んでくるので、単にモーター出力が違うだけで性能が云々ということはいえないんじゃないでしょうか。
要は加減速特性が揃っていればいいのですが、かつての小田急 2600 系みたいに、他の車輌と加減速特性が違うのを併結すると、問題になるケースはありますね。207 系がどうだったかは分かりませんが。
Posted by: 井上@kojii.net | 2005年05月13日 13:27
日時: : 2005年05月13日 13:27
207系はインバータ制御のVVVF車ですので、0番台と1000番台でモータの最大出力に差があっても、制御プログラムで加減速性能をそろえていますので併結には何ら問題ありません。
Posted by: 学研都市線沿線住民 | 2005年05月14日 14:27
日時: : 2005年05月14日 14:27
制御プログラムにバグがあったりして・・・なんて考えるのは仕事柄かな。
Posted by: 組み込み屋 | 2005年05月19日 04:58
日時: : 2005年05月19日 04:58
鉄道や回転扉などの公共的な機械設備の事故解析・計算に興味を持ち、今回の福知山線電車事故について試行しております。そのため、構造・寸法・重量などの技術的データを入手したい。それを通じてお役に立てば幸甚です。
Posted by: 大田幸雄 | 2005年06月04日 15:30
日時: : 2005年06月04日 15:30
以下千葉の総武快速のレールの写真です。6日に撮影。最高速度120kで少しカーブしています。
数百メートルにわたってレールの表面がボロボロで、さらには削れています。http://www.doro-chiba.org/nikkan_dc/n2005_01_06/photo/n6092_6.jpg
http://www.doro-chiba.org/にある写真です。
Posted by: kane | 2005年06月07日 14:04
日時: : 2005年06月07日 14:04
久しぶりにお邪魔します。
たなかさんが推測された207系0番台と1000番台の特性の差によるブレーキのクセが事実として報道されましたね。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050607i301.htm
このクセそのものがやってはいけない300R進入速度大幅超過の直接原因ではないでしょうが、ダイヤに乗れない
運転しにくい電車という事故の遠因の指摘とはいえそうですね。
Posted by: 御影すばるレガシィ | 2005年06月08日 00:18
日時: : 2005年06月08日 00:18
600メートルルールは無くなった、というわけではなく、やはり非常ブレーキで600メートル以内に止まれない場合は今でも特認を必要とするはずです。
曲線の制限速度についてはJRでは3.5*sqrt(R)を5km/h単位で丸めたものを本則と言うそうですが、このあたりの根拠はあまりよく理解していないので以下のサイトあたりが参考になるかと。
http://www1.odn.ne.jp/~aaa81350/kaisetu/tenpuku/tenpuku.htm
ちなみに、確かに207系と223系は同じモーターが使われてますが、ただでさえ高速域の加速は苦しいと言われる223系、さらに高速性能より加速度優先のギア比7.07になっている207系は...。
Posted by: fuuka | 2006年02月13日 16:12
日時: : 2006年02月13日 16:12